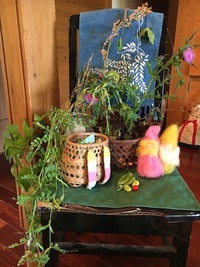2015年04月27日
4月27日の記事
虹の雲4月の例会報告です。
4月12日は今年度の始まりの会でした。

新しい学校、新しいクラス、新しい先生…、それぞれに新しい春を迎えた子どもたちは、前回から1か月しか経ってないのにも関わらず、どことなくお兄さん、お姉さんになったように思いました。子ども達は、新しい環境のなかで緊張して日々を過ごしているのかもしれませんね。目まぐるしく時が過ぎる日常のなかで、この虹の雲の存在が、子どもたちが大地にしっかり足を付け自分らしくあるよう、子ども達を支えててくれる場所になっていると思います。宇佐美先生今年度もよろしくお願い致します。
今月の歌は「おちゃをのみに」
お茶を飲みに来てください はい こんにちは
いろいろお世話になりました はい さようなら
Nさんの優しいライヤーの音色が歌と共に私たちの魂に優しく語り掛けてくれているようでした。
そしてみんなで輪になって歌いながら「お茶を飲みにきてください」のわらべ歌遊びをしました。歌いながら右に行ったり、左にいったり、お辞儀をして、こんにちは、さようなら♪子どもも大人も一緒にみんなで今月の歌を楽しみました。
【幼児クラス】
★にじみ絵

宇佐美先生のお手本は、五芒星系を描き、それがいつのまにか大地にしっかりと足をつけた「人」になりました。小さい子ども達も先生お手本をしっかり見て、思い思いに色を入れていきました。色の濃淡も様ざまで、とってもユニークで個性的なにじみ絵が出来上がりました。


★オイリュトミー
今月も元気いっぱいの幼児さんたち。馬に乗ったり、自転車にのったり、シュタープを上手に使って、軽やかに体を動かしました。
【低学年クラス】
★にじみ絵
大地にしっかりと根付き、黄色い花を咲かせたタンポポを描きました。まずは青色で空を描き、次に赤で大地に色を入れていきます。このクラスの子どもたちは、最近特に先生のお手本をよくみて、先生の話しをよく聞き、丁寧ににじみ絵に取り組んでいます。優しくて、色鮮やかで、力強いタンポポが描かれました。



★オイリュトミー
シュタープをつなげて長い列車になったり、自転車に乗ったりして会場内を元気よく動きました。シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも上手に出来ていました。


【高学年クラス】
★にじみ絵
今回は、中1、小5、小4のクラスです。さすがにお兄さん、お姉さんたち、タンポポの根の部分も丁寧に細かく筆を入れていきました。背景の青が濃すぎるようであれば、青色を筆で取り除き、そこに黄色いタンポポを描きました。そうすると、黄色が濁らず、お日様のような鮮やかな黄色いタンポポを描くことが出来ました。

★オイリュトミー
シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも、先生のお手本にならい、とても美しく動けるようになりました。さすが! お兄さん、お姉さん! です。また基本の動きに加え、3人で輪になり、シュタープをやり取りする動きをしました。回を重ねるごとに安定感が増し、スムースに動けるようになりました。


【今月の手仕事】
今月の手仕事は、イースターの卵を作りました。
春分の日の3月21日を境に太陽は月より強くなり、太陽の軌道は広がり高くなります。春分後の満月のあとの日曜日にイースターのお祝いします。今年は4月5日の日曜日がイースターをお祝いする日でしたね。
イースターエッグというように、イースターではなぜ卵をモチーフにするのでしょう? フィンランドの叙情詩「カレワラ」の中にも世界の誕生は卵からだと書いてあります。それによると、卵の殻の上の部分から空ができ、下の部分は地になり、卵黄は太陽に、卵白は月になります。それと同時に卵は永遠のシンボルであり、消えることも滅びることもない人間の本質と考えられているそうです。
子どもたちは、お家で準備してきた卵の殻に、色紙を細かくしして糊で貼り、とても可愛らしいイースターエッグを作りました。色とりどりのイースターエッグが窓辺を賑やかに彩りました。


【お話し会】
今回の午後の時間は、虹の雲に興味を持っていただいた方に参加していただき、お話し会を行いました。学校のこと、シュタイナー教育のこと、オイリュトミーやにじみ絵のことについてお話ししました。また、宇佐美先生には主にシュタイナー教育のことについてお話しいただきました。
インターネットや電子ゲームがこれだけ普及する現代、個人的にも日々子育てしにくい社会だな…と実感しています。学校の25人のクラスでゲームを持っていないのはうちの子だけ、特に男の子たちはゲームに魂を吸い取られてしまっている様子です…。お友達と遊ぶのもゲームありき。友達と遊んでるのではなく、ゲームに遊ばれている今の子どもたち…、見ていて本当に気の毒に思います。大人が子どもたちをそうしてしまっているのですよね。だからこそ、虹の雲の活動が子ども達にとってとても有意義な時間だなと思います。
お話し会では宇佐美先生にシュタイナーの七年周期説についてお話しいただきました。0~7歳までは体・生命体を育む時期であること。7~14歳までは感情の部分であるアストラル体が形成され、14~21歳までは思考の力が形成されていきます。例えば、2、3歳の小さなお子さんに学習的要素のある勉強をさせてしまうと、体が発達する前に頭だけ発達してしまい、後に体に異常をきたすようなことがあります。
また、子ども達に与えるおもちゃについても話題に上りました。特に男の子に人気かと思いますが、レゴやKAPLAなど、カタチが決まっていて、それを組み合わせていくようなおもちゃは、子どもたちから想像力を奪ってしまうそうです。(どっちとも我が家にあります~汗)ファンタジーも人生も、決まったことの組み合わせではなく、予期せぬことの連続ですよね。
だからこそ、想像力を育むことはとても大切なことだと考えます。
今回初めて参加された方からも様ざまな質問もあり、宇佐美先生には実例を交えながら細やかにお答えいただきました。現メンバーの私たちも、シュタイナー教育の基礎を見つめなおすきっかけとなりました。宇佐美先生本当にありがとうございました。今回お話し会に参加してくださった方より、来月の体験のお申込みをいただきました。また新しいご縁が生まれそうで今から楽しみにしています。
次回の例会のご案内です。
5月10日(日)10:00~ 熊本友の会(熊本市中央区渡鹿6-5-82)
問い合わせ:090-9722-8862
t.momiji@ezweb.ne.jp(照山)
4月12日は今年度の始まりの会でした。

新しい学校、新しいクラス、新しい先生…、それぞれに新しい春を迎えた子どもたちは、前回から1か月しか経ってないのにも関わらず、どことなくお兄さん、お姉さんになったように思いました。子ども達は、新しい環境のなかで緊張して日々を過ごしているのかもしれませんね。目まぐるしく時が過ぎる日常のなかで、この虹の雲の存在が、子どもたちが大地にしっかり足を付け自分らしくあるよう、子ども達を支えててくれる場所になっていると思います。宇佐美先生今年度もよろしくお願い致します。
今月の歌は「おちゃをのみに」
お茶を飲みに来てください はい こんにちは
いろいろお世話になりました はい さようなら
Nさんの優しいライヤーの音色が歌と共に私たちの魂に優しく語り掛けてくれているようでした。
そしてみんなで輪になって歌いながら「お茶を飲みにきてください」のわらべ歌遊びをしました。歌いながら右に行ったり、左にいったり、お辞儀をして、こんにちは、さようなら♪子どもも大人も一緒にみんなで今月の歌を楽しみました。
【幼児クラス】
★にじみ絵

宇佐美先生のお手本は、五芒星系を描き、それがいつのまにか大地にしっかりと足をつけた「人」になりました。小さい子ども達も先生お手本をしっかり見て、思い思いに色を入れていきました。色の濃淡も様ざまで、とってもユニークで個性的なにじみ絵が出来上がりました。


★オイリュトミー
今月も元気いっぱいの幼児さんたち。馬に乗ったり、自転車にのったり、シュタープを上手に使って、軽やかに体を動かしました。
【低学年クラス】
★にじみ絵
大地にしっかりと根付き、黄色い花を咲かせたタンポポを描きました。まずは青色で空を描き、次に赤で大地に色を入れていきます。このクラスの子どもたちは、最近特に先生のお手本をよくみて、先生の話しをよく聞き、丁寧ににじみ絵に取り組んでいます。優しくて、色鮮やかで、力強いタンポポが描かれました。



★オイリュトミー
シュタープをつなげて長い列車になったり、自転車に乗ったりして会場内を元気よく動きました。シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも上手に出来ていました。


【高学年クラス】
★にじみ絵
今回は、中1、小5、小4のクラスです。さすがにお兄さん、お姉さんたち、タンポポの根の部分も丁寧に細かく筆を入れていきました。背景の青が濃すぎるようであれば、青色を筆で取り除き、そこに黄色いタンポポを描きました。そうすると、黄色が濁らず、お日様のような鮮やかな黄色いタンポポを描くことが出来ました。

★オイリュトミー
シュタープを頭の上に乗せて歩く動きも、先生のお手本にならい、とても美しく動けるようになりました。さすが! お兄さん、お姉さん! です。また基本の動きに加え、3人で輪になり、シュタープをやり取りする動きをしました。回を重ねるごとに安定感が増し、スムースに動けるようになりました。


【今月の手仕事】
今月の手仕事は、イースターの卵を作りました。
春分の日の3月21日を境に太陽は月より強くなり、太陽の軌道は広がり高くなります。春分後の満月のあとの日曜日にイースターのお祝いします。今年は4月5日の日曜日がイースターをお祝いする日でしたね。
イースターエッグというように、イースターではなぜ卵をモチーフにするのでしょう? フィンランドの叙情詩「カレワラ」の中にも世界の誕生は卵からだと書いてあります。それによると、卵の殻の上の部分から空ができ、下の部分は地になり、卵黄は太陽に、卵白は月になります。それと同時に卵は永遠のシンボルであり、消えることも滅びることもない人間の本質と考えられているそうです。
子どもたちは、お家で準備してきた卵の殻に、色紙を細かくしして糊で貼り、とても可愛らしいイースターエッグを作りました。色とりどりのイースターエッグが窓辺を賑やかに彩りました。


【お話し会】
今回の午後の時間は、虹の雲に興味を持っていただいた方に参加していただき、お話し会を行いました。学校のこと、シュタイナー教育のこと、オイリュトミーやにじみ絵のことについてお話ししました。また、宇佐美先生には主にシュタイナー教育のことについてお話しいただきました。
インターネットや電子ゲームがこれだけ普及する現代、個人的にも日々子育てしにくい社会だな…と実感しています。学校の25人のクラスでゲームを持っていないのはうちの子だけ、特に男の子たちはゲームに魂を吸い取られてしまっている様子です…。お友達と遊ぶのもゲームありき。友達と遊んでるのではなく、ゲームに遊ばれている今の子どもたち…、見ていて本当に気の毒に思います。大人が子どもたちをそうしてしまっているのですよね。だからこそ、虹の雲の活動が子ども達にとってとても有意義な時間だなと思います。
お話し会では宇佐美先生にシュタイナーの七年周期説についてお話しいただきました。0~7歳までは体・生命体を育む時期であること。7~14歳までは感情の部分であるアストラル体が形成され、14~21歳までは思考の力が形成されていきます。例えば、2、3歳の小さなお子さんに学習的要素のある勉強をさせてしまうと、体が発達する前に頭だけ発達してしまい、後に体に異常をきたすようなことがあります。
また、子ども達に与えるおもちゃについても話題に上りました。特に男の子に人気かと思いますが、レゴやKAPLAなど、カタチが決まっていて、それを組み合わせていくようなおもちゃは、子どもたちから想像力を奪ってしまうそうです。(どっちとも我が家にあります~汗)ファンタジーも人生も、決まったことの組み合わせではなく、予期せぬことの連続ですよね。
だからこそ、想像力を育むことはとても大切なことだと考えます。
今回初めて参加された方からも様ざまな質問もあり、宇佐美先生には実例を交えながら細やかにお答えいただきました。現メンバーの私たちも、シュタイナー教育の基礎を見つめなおすきっかけとなりました。宇佐美先生本当にありがとうございました。今回お話し会に参加してくださった方より、来月の体験のお申込みをいただきました。また新しいご縁が生まれそうで今から楽しみにしています。
次回の例会のご案内です。
5月10日(日)10:00~ 熊本友の会(熊本市中央区渡鹿6-5-82)
問い合わせ:090-9722-8862
t.momiji@ezweb.ne.jp(照山)
2019年3月例会のご案内 こころとからだをは育むアートプロジェクト
例会のご報告
「こころとからだを育むアートプロジェクト」始まります!
2017年10月例会
7月例会~赤紫蘇の香りとともに~
2017年5月例会
例会のご報告
「こころとからだを育むアートプロジェクト」始まります!
2017年10月例会
7月例会~赤紫蘇の香りとともに~
2017年5月例会
Posted by 虹の雲 at 23:55│Comments(0)
│例会